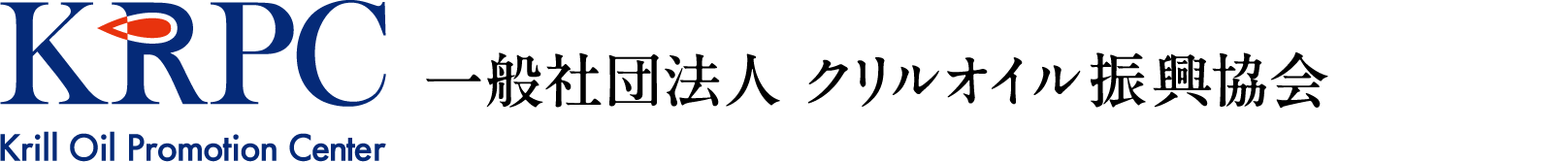KRPC Ambassador Letter クリルオイルの健康促進と疾病予防の最新情報
[Vol.9] 健康な細胞が、健康な身体をつくる Part7細胞間のコミュニケーションは「生命の調和」の土台
前回(Vol.8)までは、細胞膜の9つの役割のうち
「1.物質の選択的透過性」
「2.情報伝達(シグナル伝達)」
「3.細胞の保護・防御機能:守りの壁」
「4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み」
について取り上げ、それらの特徴が損なわれた場合に身体にどのような不調や影響が出るのかをお伝えしました。
今回は、「5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」」についてご説明していきます。
細胞間のコミュニケーションは「生命の調和」の土台
私たちの身体は、およそ37兆個の細胞から構成されています。これらの細胞は、筋肉、神経、血管、皮膚、免疫など、役割の異なるチームに分かれ、それぞれの仕事を担っています。しかし、これらの細胞が単独で勝手に働いているわけではありません。
すべての細胞は、まるで「美しい音楽を奏でるオーケストラ」のように、他の細胞の動きを感じ取り、自らの行動を調整することで、全体としてバランスの取れた役割を果たしています。これこそが「細胞間コミュニケーション」の力です。
この働きによって、私たちの身体は環境の変化やストレスに対応し、損傷を修復し、免疫を働かせ、美しい肌や健康な臓器を維持することができるのです。
今回は、細胞膜が担っている9つの役割のうち、「5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」」についての機能が損なわれたときに、私たちの身体にはどのような不調や変化が現れるのかをご説明していきます。
【細胞膜の9つの役割】
- 1.物質の選択的透過:必要なものだけを通す「出入り口の管理人」
- 2.情報伝達(シグナル伝達):アンテナと指令センター
- 3.細胞の保護・防御機能:守りの壁
- 4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み
- 5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」
- 6.エネルギー代謝・物質輸送:栄養やエネルギーの「通路」
- 7.細胞の増殖や分化の調節:(成長や分裂をコントロール)
- 8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別
- 9.細胞内外の環境のバランス維持:恒常性の維持
コミュニケーションの起点は細胞膜にある
細胞膜には、以下のような重要な構造があります
| 受容体(レセプター) | ホルモンやサイトカインをキャッチし、細胞内部に「指令」を伝えます。 |
|---|---|
| イオンチャネル・ トランスポーター |
外部からの刺激を電気信号として変換・伝達します。 |
| 細胞接着分子* (カドヘリン、インテグリンなど) |
細胞と細胞を物理的につなぎ、位置や形を保ちます。 |
* 細胞は、ただバラバラに存在しているわけではなく、身体の中で正しい場所にとどまり、他の細胞と協力しながら働くために、「つなぐ仕組み」が必要です。細胞接着分子は、その“のり”や“接続パーツ”のような役割によって、「細胞と細胞」あるいは「細胞とまわりの環境」をくっつける働きをする、たんぱく質の一種です。
この細胞膜の質(流動性や構成脂質のバランス)が劣化すると、細胞間の意思疎通に支障をきたし、情報伝達の誤作動や遅延を招くのです。
細胞間コミュニケーションの仕組み
細胞間のコミュニケーションは、大きく分けて以下のようなメカニズムによって行われています
① 化学的シグナルによる伝達
| ホルモン | 血流にのって全身に届く。 例:インスリン、エストロゲン、コルチゾールなど |
|---|---|
| サイトカイン・ケモカイン | 主に免疫細胞が出す情報分子で、炎症や免疫反応を調整します。 |
| 神経伝達物質 | 神経細胞から放出され、すぐ近くの細胞に素早く作用します。 例:アセチルコリン、ドーパミンなど |
② 物理的な接触による伝達
| 細胞接着分子 | 細胞と細胞を物理的につなぎ、情報交換を助けます。 |
|---|---|
| ギャップ結合 | 隣接する細胞の間に小さな通路を形成し、イオンや小分子をやりとりします。 |
③ 細胞外小胞(エクソソームなど)による伝達
| エクソソーム | 細胞から分泌される小さな膜に包まれた小胞で、遠くの細胞にメッセージを届けます。 |
|---|
細胞は孤立していない
なぜチームプレーがなぜ重要なのかというと、細胞は「自分の役割をきちんと果たす」だけでなく、「周囲の細胞と連携しながらタイミングよく働く」ことで初めて、身体としての一体的な働きが生まれます。
例えば、傷ついた皮膚の再生には、皮膚細胞、線維芽細胞、免疫細胞が連携して「修復モード」に切り替える必要があります。
血糖値が上がると、膵臓のβ細胞がインスリンを分泌し、筋肉や肝臓に「糖を取り込め」と指示します。
危険なウイルスが侵入したら、免疫細胞同士が「ここに敵がいる」「攻撃せよ」「過剰な反応はやめよ」などの指示を出し合って、過不足のない免疫反応を展開します。
つまり、細胞間の情報伝達がうまくいっている=身体の内部がよく統制されている状態なのです。
5. 細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」
生活習慣や生活環境による影響の可能性
- 慢性的なストレス
- 睡眠不足
- 過剰な糖分・脂質の摂取
- 環境汚染物質や喫煙
自律神経やホルモンバランスが崩れ、神経細胞や免疫細胞同士の情報のやりとりが不安定になります。これにより、炎症反応の制御が効かなくなったり、疲労感や集中力低下につながります。
細胞の再生や修復に必要なシグナル伝達が妨げられ、連携が滞る原因になります。
慢性炎症を引き起こし、細胞間の正常なシグナルがノイズにより遮られやすくなります。
「糖化反応*(AGEsの蓄積)」により、細胞膜や受容体が変性。情報の伝達経路が妨げられ、細胞が本来の指示を受け取れなくなることがあります。
*「糖」と「たんぱく質」や「脂質」が結びついてしまう反応のことです。結合が進むとAEGs(終末糖化産物)という老化物質ができます。AGEsが蓄積すると、細胞や組織の機能を劣化させてしまいます。
細胞膜や受容体にダメージを与え、コミュニケーション能力を低下させる要因になります。
活性酸素が細胞膜や細胞接着分子を酸化し、細胞同士の「つながり」が劣化します。特に呼吸器や皮膚の細胞連携が弱まり、慢性的な炎症やバリア機能の破綻につながっていきます。
細胞膜への影響
細胞間コミュニケーションの多くは、細胞膜上の「受容体」や「情報伝達チャネル」を介して行われます。これらは主にリン脂質とタンパク質で構成されていて、細胞膜の質が低下すると以下のような問題が起こります。
細胞間コミュニケーションに不可欠な「受容体(レセプター)」や「細胞接着分子」は細胞膜上に存在します。
① 情報伝達物質が正しく受容されない(ホルモン抵抗性、炎症シグナルの誤作動など)
② 細胞同士の接着力が弱まり、組織の一体感が失われる(肌のキメの乱れ、免疫細胞の暴走など)
③ 特に膜の流動性や脂質組成のバランスが崩れると、シグナルのやりとりが遅れたり誤作動を起こしたりします。
細胞膜の質が劣化すると、情報を正確に受け取ったり伝えたりする能力が低下します。
例えば、オメガ3系脂肪酸が不足すると、細胞膜の柔軟性が低下し、神経伝達や免疫調整機能がスムーズに働かなくなります。
機能の低下による不具合
・信号の誤送信や伝達の遅延により、細胞が不適切な反応をします。
例:アレルゲンに対する過剰反応
必要な情報が伝わらず、細胞が的確な反応を示さなくなります。
例:免疫細胞が異常に反応したり、逆に反応しなくなったりします。
・組織の一体性の低下
例:腸の細胞間連携が弱まり、バリア機能が損なわれます。
リーキーガット症候群:各細胞のタイミングや行動がずれ、組織全体の機能が低下します。
・治癒や修復の遅延(細胞からの「修復開始シグナル」が届かない)
細胞の分化・修復・増殖のバランスが崩れ、老化や組織の劣化が進行します。
例:外傷や炎症後の肌の再生遅延
線維芽細胞や免疫細胞間の信号がスムーズに届かないと、コラーゲン合成や炎症鎮静が遅れ、傷が治りにくくなります。
起こりやすい不調や目に見える変化
- 疲れやすい、集中力の低下
- 慢性的な倦怠感や免疫力の低下
- 肌のキメの乱れやハリの喪失(皮膚細胞間の連携が弱まる)
- 肌荒れや敏感肌(バリア機能や炎症調節の不全)
疲労感が抜けない、頭がぼーっとする(神経細胞間の伝達不良)
風邪を引きやすい、炎症が長引く(免疫細胞の連携異常)
肌のざらつき、くすみ、毛穴の開き、肌の乾燥(表皮細胞間の接着や情報交換の乱れ)
便秘や下痢が交互に起こる(腸上皮細胞と腸内神経系の連携不全)
関連する疾患や症状、病態(病気につながる体内の状態)
| 項目 | 説明 | 主な影響・特徴 |
|---|---|---|
| 神経変性疾患 (例:アルツハイマー病) |
神経細胞間の情報伝達(シナプス伝達)の障害により、記憶や認知、行動の異常が生じる。 | 記憶障害、判断力の低下、人格変化など。アミロイドβやタウタンパクの蓄積も関与。 |
| 自閉スペクトラム症 (ASD) |
神経細胞の接続や情報伝達の異常により、社会的コミュニケーション能力や柔軟な思考に障害がみられることがある。 | 社会的交流の困難、反復行動、感覚過敏。細胞間の信号伝達の不均衡が報告されている。 |
| 炎症性疾患 (例:慢性関節リウマチ) |
免疫細胞間の異常な情報伝達により、攻撃対象を誤って自己組織と認識し、炎症が長期化する。 | 関節の腫れ・痛み、組織破壊。サイトカインによる過剰な炎症反応が見られる。 |
| 皮膚バリア異常 (例:アトピー性皮膚炎) |
角化細胞や免疫細胞間の情報連携が乱れ、バリア機能の維持や異物への防御がうまく働かなくなる。 | 皮膚の乾燥、かゆみ、炎症の慢性化。皮膚の細胞間連携の乱れによるトラブル。 |
| 心血管疾患 | 血管内皮細胞や免疫細胞、平滑筋細胞の情報共有が乱れることで、動脈硬化や血栓形成が進行する。 | 動脈の狭窄や破裂、血流障害。慢性炎症や異常な細胞間シグナルが関与。 |
| 加齢による機能低下 | 細胞間コミュニケーションの効率が低下することで、全身の調整機能が衰え、老化現象や慢性疾患が進行しやすくなる。 | 修復力の低下、免疫反応の鈍化、情報伝達速度の減少など。慢性炎症とも関連。 |
美容・アンチエイジング面での影響
- 肌のターンオーバーの乱れ
- 肌のハリ・弾力低下
- 慢性的な赤み・肌荒れ
肌細胞間の連携が崩れると、水分保持力や再生力が低下し、乾燥・小ジワ・たるみなどの老化サインが現れやすくなります。
表皮細胞同士の情報伝達が滞り、古い角質がたまりやすくなり、肌の透明感や滑らかさが損なわれます。
コラーゲン産生やターンオーバーも、細胞間の情報伝達に依存していて、その乱れが肌のハリや明るさの低下につながります。
線維芽細胞間のコミュニケーション不全で、コラーゲンやエラスチンの合成が抑制されます。
炎症性サイトカインの暴走により肌荒れや慢性的な赤み・敏感肌になる可能性も。免疫細胞や角化細胞の連携が乱れ、炎症が長引きやすくなります。
例:マスクによる肌荒れがなかなか治らないのは?
→ 表皮細胞と免疫細胞間のバランスが乱れていると、刺激を鎮めるための信号が行き届かず、炎症状態が慢性化します。
今回のまとめ
細胞同士が「協調」して働くには、以下のような伝達手段が不可欠です。
- 細胞膜の受容体を介した情報伝達
- 細胞接着分子による物理的な接触と情報共有
- サイトカイン・ホルモン・神経伝達物質などの分泌による遠隔伝達
- 細胞外小胞(エクソソームなど)による分子輸送
これらのプロセスが正しく機能するには、細胞膜の質が非常に重要です。
なぜならば…
- 細胞が情報を受け取る「受容体」は細胞膜に埋め込まれています。
- 細胞が情報を出す「伝達物質」の放出は、細胞膜を通して細胞の外に出されます。
- エクソソームや細胞接着分子の働きも、細胞膜の質に大きく左右されます。
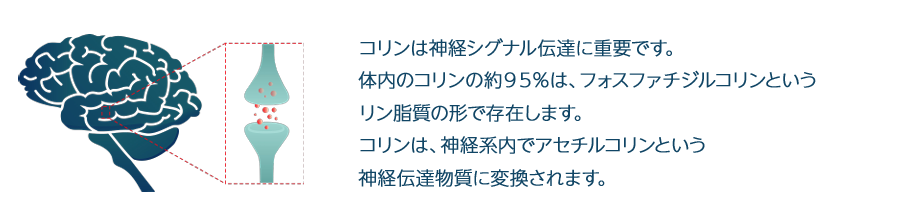
© AKER BIOMARINE, Inc
クリルオイルに含まれるリン脂質型オメガ3(EPA・DHA)は、細胞膜の流動性を高め、受容体の働きを円滑にするとされています。
細胞膜の構造安定性が向上することで、神経細胞や免疫細胞の信号伝達がスムーズになり、細胞同士の協調が保たれやすくなります。
脳の神経どうしがスムーズにやりとりできるように、情報を受け渡す場所の柔らかさや動きやすさに関わっていると考えられています。
免疫細胞が連携して働くときに大切な、細胞の表面のかたちやくっつき方に関わっていると考えられています。
-
- Ulven SM, Holven KB. Comparison of bioavailability of krill oil versus fish oil and health effect. Vasc Health Risk Manag. 2015 Aug 28;11:511-24. doi: 10.2147/VHRM.S85165. PMID: 26357480; PMCID: PMC4559234.
- Dighriri IM, Alsubaie AM, Hakami FM, Hamithi DM, Alshekh MM, Khobrani FA, Dalak FE, Hakami AA, Alsueaadi EH, Alsaawi LS, Alshammari SF, Alqahtani AS, Alawi IA, Aljuaid AA, Tawhari MQ. Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Brain Functions: A Systematic Review. Cureus. 2022 Oct 9;14(10):e30091. doi: 10.7759/cureus.30091. PMID: 36381743; PMCID: PMC9641984.
- Liu Y, Robinson AM, Su XQ, Nurgali K. Krill Oil and Its Bioactive Components as a Potential Therapy for Inflammatory Bowel Disease: Insights from In Vivo and In Vitro Studies. Biomolecules. 2024 Apr 6;14(4):447. doi: 10.3390/biom14040447. PMID: 38672464; PMCID: PMC11048140.
- Ulven SM, Kirkhus B, Lamglait A, Basu S, Elind E, Haider T, Berge K, Vik H, Pedersen JI. Metabolic effects of krill oil are essentially similar to those of fish oil but at lower dose of EPA and DHA, in healthy volunteers. Lipids. 2011 Jan;46(1):37-46. doi: 10.1007/s11745-010-3490-4. Epub 2010 Nov 2. PMID: 21042875; PMCID: PMC3024511.
- Ulven SM, Holven KB. Comparison of bioavailability of krill oil versus fish oil and health effect. Vasc Health Risk Manag. 2015 Aug 28;11:511-24. doi: 10.2147/VHRM.S85165. PMID: 26357480; PMCID: PMC4559234.
- Mun JG, Legette LL, Ikonte CJ, Mitmesser SH. Choline and DHA in Maternal and Infant Nutrition: Synergistic Implications in Brain and Eye Health. Nutrients. 2019 May 21;11(5):1125. doi: 10.3390/nu11051125. PMID: 31117180; PMCID: PMC6566660.
- Blusztajn JK, Liscovitch M, Richardson UI. Synthesis of acetylcholine from choline derived from phosphatidylcholine in a human neuronal cell line. Proc Natl Acad Sci U S A. 1987 Aug;84(15):5474-7. doi: 10.1073/pnas.84.15.5474. PMID: 3474663; PMCID: PMC298880.
- Beydoun MA, Kaufman JS, Satia JA, Rosamond W, Folsom AR. Plasma n-3 fatty acids and the risk of cognitive decline in older adults: the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Am J Clin Nutr. 2007 Apr;85(4):1103-11. doi: 10.1093/ajcn/85.4.1103. PMID: 17413112.
過去の記事を読む
- [Vol.18]
健康を基本から見直す“脂質ケア”という新習慣 - [Vol.17]
冬に知っておきたい脂肪の新常識!減らすより整える。身体が自然に選ぶ脂肪の正しい活用法 - [Vol.16]
身体の“だるさ”の季節リレーを止める!身体のスイッチを入れて、季節を超えて元気になる - [Vol.15]
季節を超えて続く“夏疲れ”。秋冬の不調、その正体は? - [Vol.14]
胃もたれとあぶら(脂質)の関係 -オメガ3脂肪酸の形(構造)は1種類ではない - [Vol.13]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part11 - [Vol.12]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part10 - [Vol.11]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part9 - [Vol.10]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part8 - [Vol.8]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part6 - [Vol.7]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part5 - [Vol.6]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part4 - [Vol.5]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part3 - [Vol.4]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part2 - [Vol.3]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part1 - [Vol.2]
細胞レベルで健康をサポートするクリルオイル - [Vol.1]
クリルの生態とクリルオイルの魅力について