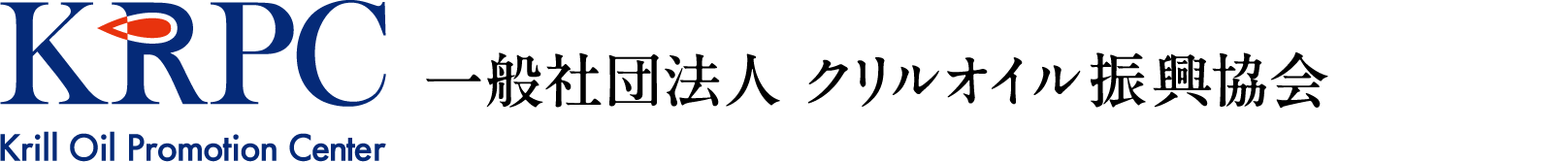KRPC Ambassador Letter クリルオイルの健康促進と疾病予防の最新情報
[Vol.12] 健康な細胞が、健康な身体をつくる Part10「健康」は、細胞のチームプレーで守られている
前回(Vol.10)までは、細胞膜の9つの役割のうち
「1.物質の選択的透過性」
「2.情報伝達(シグナル伝達)」
「3.細胞の保護・防御機能:守りの壁」
「4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み」
「5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」」
「6.エネルギー代謝・物質輸送:栄養やエネルギーの“通路”」
「7.細胞の増殖や分化の調節:成長や分裂をコントロール」
について取り上げ、それらの特徴が損なわれた場合に身体にどのような不調や影響が出るのかをお伝えしました。
今回は、「8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別」についてご説明していきます。
「健康」は、細胞のチームプレーで守られている
私たちの身体の中では、毎日たくさんの「細胞同士の出会い」が繰り返されています。細胞と細胞が協力し合い、すれ違い、ときに外から入り込んだ異物と向き合います。そんな場面で欠かせないのが、細胞一つひとつが持っている「 名札 」です。その名札には「私はあなたの仲間です」「私は異物です」といった大切な情報が刻まれ、免疫細胞はそれを手がかりに瞬時に判断を下しています。
多くの人たちにとって「免疫」とは、風邪や感染症から身を守る“防御の力”というイメージがあるかもしれません。もちろんそれも免疫の大切な働きですが、その根底にはもっと基本的で欠かせない仕組みがあります。それは、細胞が持つ「名札」を手がかりに、「自分」と「自分以外」を見分ける力です。免疫の働きは、まさにここから始まるのです。
もし、この名札が読みづらかったり、誤った情報を掲げていたらどうなるでしょう。仲間を敵と勘違いして攻撃してしまったり、逆に外敵を見逃してしまったり、身体の調和はあっという間に崩れてしまいます。ふだん意識することのない小さな仕組みですが、私たちの健康や若々しさを支えているのは、この繊細な“名札のやり取り”に他なりません。
今回は、細胞膜が担っている9つの役割のうち、「8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別」についての機能が損なわれたときに、私たちの身体にはどのような不調や変化が現れるのかをご説明していきます。
【細胞膜の9つの役割】
- 1.物質の選択的透過:必要なものだけを通す「出入り口の管理人」
- 2.情報伝達(シグナル伝達):アンテナと指令センター
- 3.細胞の保護・防御機能:守りの壁
- 4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み
- 5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」
- 6.エネルギー代謝・物質輸送:栄養やエネルギーの「通路」
- 7.細胞の増殖や分化の調節:(成長や分裂をコントロール)
- 8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別
- 9.細胞内外の環境のバランス維持:恒常性の維持
免疫のいろは。
- 一言でいうと?
- 免疫の基本的な役割とは?
- 免疫の仕組みとは?
- 自然免疫
- 獲得免疫
- 免疫の本質とは?
- 「自分」と「自分以外」を見分ける
- 必要なときに迅速に反応し、不要なときは静まる
- 恒常性(ホメオスタシス*)を維持する
「身体を守る防御システム」 のことです。
| 外敵から守る | ウイルス、細菌、寄生虫などが侵入してきたときに排除します。 |
|---|---|
| 体内の異常を見つける | がん細胞など、自分の中で生まれた異常な細胞を監視し、排除します。 |
| バランスを保つ | 必要以上に反応しないように調整し、炎症が長引かないようにします。 |
生まれつき備わっている「即時対応型の防御」。皮膚・粘膜、白血球(マクロファージなど)がこれにあたります。
一度出会った病原体を「記憶」し、次に出会ったときには素早く強力に対応する仕組みです。
免疫は単に身体を守るために戦うシステムではなく、体内の秩序を保つための高度な見極めと調整の仕組み です。
免疫は、自分の身体を構成する正常な細胞と、ウイルス・細菌・異常な細胞(がん細胞など)を識別します。
例えると・・・
身体の細胞はみんな 社員証を持った会社の社員。
外から来たウイルスや細菌は 社員証を持っていない不審者。
がん細胞は 社員証が壊れたり、偽造された社員。
警備員=免疫細胞は、社員証を確認して仲間と不審者を見分けるようなイメージです。
敵が現れたときは素早く攻撃し、戦いが終わればすぐに静まり、過剰な炎症や自己攻撃を避けます。
この「見分ける力」と「調整力」を通じて、身体の内側の環境を安定に保ち、健康を維持します。免疫は、この恒常性の一部を担っています。
* 恒常性(ホメオスタシス)とは、外の環境が変わっても、身体の中の状態を一定に保つ働きのことです。具体例としては、外が寒くても暑くても体温を約36~37℃に保つ働きをしています。
細胞の名札のいろは?
私たちの身体の中には、数10兆個もの細胞が存在しています。それぞれの細胞は、ただそこにあるだけではありません。「これは自分の細胞です」「これは異物です」と見分けるために、細胞の表面には小さな「名札」がついています。
- 名札とは何?
- 名札はすべての細胞にある?
- まとめ
- 細胞の名札は、身体の免疫や健康を守る小さな案内板のようなものです。
正式には 「細胞表面マーカー」 と呼ばれます。
タンパク質や糖鎖*などでできていて、細胞ごとに異なる情報を掲示しています。
この名札を目印にして、免疫細胞は「味方」と「敵」を判断します。
* 糖鎖とは、細胞の表面にある「糖でできた鎖状の構造」で、細胞の名札やアンテナのように情報交換や識別を助けています。
ほとんどの細胞にはありますが、赤血球のように簡略化された細胞もあります。
名札の種類や情報量は、細胞の種類や役割によって異なります。
8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別
生活習慣や生活環境による影響の可能性
免疫系は非常にデリケートなシステムであり、食事・睡眠・ストレス・運動習慣、さらには環境因子まで、多方面からの影響を受けて働きが変化します。これらの要素は細胞膜やホルモン、シグナル伝達に作用し、免疫細胞の「自他の区別(自己と非自己の認識)」や「調整力」に直結します。
- 食生活の影響
- 高脂肪・高糖質の食事
- 過剰な飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は、細胞膜の柔軟性や安定性に影響を与える可能性があることが示されています(※参考:1,2,3)。
- 細胞膜上にある「受容体」や「MHC(主要組織適合抗原=名札のような分子)」の働きが鈍くなり、免疫細胞が敵か味方かを正しく見分けにくくなります。
- 高糖質の食事は、体内で糖とたんぱく質が結びつく「糖化反応(AGEsの生成)」を進めます。この影響で、細胞の表面や情報を受け取る部分(受容体)が変化し、免疫の働きがうまく調整できなくなることがあります。
- 添加物の影響
- 乳化剤や保存料の一部は、腸内細菌のバランスに影響を与え、腸粘膜バリア機能を弱める可能性があることが報告されています(※参考:4,5,6)。
これにより異物が体内に入り込みやすくなり、免疫の「誤作動(過剰反応やアレルギー)」が増えやすくなります。 - これにより腸のバリア機能が低下し、不要な分子が体内に入りやすくなり、免疫細胞が「敵」と「味方」を見誤るリスクが増します。
- 一部の添加物は直接的に細胞膜の脂質二重層に取り込まれ、膜の流動性や透過性を変える可能性もあります(※参考:7)。
- 睡眠・ストレスの影響
- 睡眠不足
- 睡眠中に分泌される「メラトニン」は抗酸化作用を持ち、細胞膜を酸化ストレスから守ります(※参考:8,9)。
睡眠不足で分泌が減ると、細胞膜が酸化しやすくなり(※参考:10)「自他認識の精度」が落ちます。 - 深い睡眠は免疫細胞の増殖や分化に必要なサイトカイン*の産生を促しますが、睡眠不足ではこの調整が乱れます(※参考:11,12)。
- 強いストレス
- ストレスで分泌される「コルチゾール」は短期的には炎症を抑える役割を持ちますが、慢性的に高い状態が続くと免疫細胞の働きを抑制し、敵に反応しにくくなってしまいます。
- 免疫が正しく“攻撃対象”と“自分”を見分けられなくなると、自己組織に対しても攻撃してしまう可能性があります(自己免疫疾患のリスク)。
- 慢性的ストレス
- コルチゾールは本来、炎症を抑えるブレーキ役ですが、過剰分泌が続くと免疫抑制に傾き、感染症リスクが高まります。
- 一方でストレスに伴う交感神経優位は、炎症性サイトカイン*の過剰産生を招き、自己免疫疾患や慢性炎症の引き金になります。
- 外的環境の影響
- 大気汚染(PM2.5、排気ガスなど)
- 粒子が体内に入ると、細胞膜の脂質を酸化させる可能性があり、免疫細胞が異物や自分の細胞を見分ける情報の出し方に影響する場合があります(※参考:13,14)。
- アレルギー反応や自己免疫のリスク上昇とも関連が報告されています(※参考:15,16)。
- 紫外線
- 紫外線は皮膚細胞膜の脂質を酸化し、DNAにもダメージを与えます。
- 適度な紫外線はビタミンD合成を介して免疫をサポートしますが、浴びすぎると免疫抑制を引き起こします。
- 化学物質(農薬・重金属・プラスチック由来物質など)
- 化学物質(農薬・重金属・プラスチック由来物質など)は、細胞膜の脂質二重層に取り込みやすく、膜の柔軟性や透過性に影響を与える可能性があります。
- 長く体内にあると、免疫細胞の「名札(抗原提示分子)」の形や出し方が変わり、「自分」と「自分でないもの」を見分ける働きが乱れる原因になることがあります(※参考:17,18,19,20)。
- 酷暑(高温環境)の影響
- 体温調節負荷と免疫機能の低下
- 高温環境下では身体は汗をかき、循環系・水分バランス・電解質バランスを維持するためにエネルギーを消費します。
- この負荷により、免疫細胞の働きが一時的に低下し、感染症リスクが高まることがあります。
- 細胞膜やホルモンへの影響
- 高温は細胞膜の流動性に影響を与え、細胞膜に埋め込まれた受容体や輸送体の機能が変化する可能性があります。
- また、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が増えることで、免疫の調整機能が乱れやすくなります。
- 脱水・熱ストレスによる炎症誘発
- 脱水状態になると血液が濃縮され、血流や酸素供給が不安定になります。
- 細胞は酸化ストレスを受けやすくなり、軽度の炎症状態が続くことで免疫の誤作動(過剰反応や弱体化)につながることがあります。
* サイトカインとは,細胞同士が「情報を伝えるために出すタンパク質」の総称です。免疫細胞やその他の細胞が分泌し、周囲の細胞に「戦え」「修復せよ」といった指令を送ります。身体の司令塔のような役割を果たします。
* 炎症性サイトカイン=炎症を起こす指令を出すタンパク質。防御には必要ですが、出すぎると病気や老化の進行に関与すると考えられています。
酷暑は単に暑いだけでなく、身体や免疫の調整システムに負担をかけます。
十分な水分補給や適切な休息、冷却環境の確保が、免疫の精度と安定性を守るうえでとても重要です。
まとめ
私たちの生活習慣や環境は、細胞膜の健康やホルモンの働きを通じて、免疫系の「自分と外の区別」や「調整の仕組み」に影響を及ぼします。
言い換えれば、普段の食事や睡眠、ストレスへの向き合い方、環境への配慮といった積み重ねが、免疫の働きの確かさと安定性を形づくっているのです。
細胞膜への影響
免疫細胞の表面には、「MHC(主要組織適合抗原)」や「受容体」と呼ばれる分子がびっしりと並んでいます。
これらは、いわば 名札やセンサー のような役割を果たしており、
| MHC分子 | 「この細胞は自分の仲間か、異物か」を周囲の免疫細胞に伝える。 |
|---|---|
| 受容体 | 細菌・ウイルス・異常な細胞から出るシグナルをキャッチするアンテナ。 |
といった働きがあります。
- 細胞膜の脂質組成が乱れると何が起こるか?
- MHCや受容体の配置が乱れる
- 認識の精度が低下する
- 脂質の種類による影響
- トランス脂肪酸:
- 酸化脂質(過酸化脂質など)が多い場合:
- まとめ
細胞膜は主に脂質(リン脂質・コレステロールなど)でできています。
細胞膜の脂質バランスが崩れると、以下の問題が生じます。
本来はきれいに並んでいる分子が、細胞膜が硬くなったり歪んだりすることで動きにくくなり、正しい位置に配置されにくくなります。
アンテナの角度がずれてしまうように、外部シグナルを正しくキャッチできなくなります。その結果、
- 病原体や異常な細胞を「見逃す」
- 逆に「自分自身の細胞」を誤って攻撃する(自己免疫反応)
といったトラブルにつながりやすくなります。
細胞膜の中に入り込むと、もともとの柔らかい脂質の間に硬い棒のように入り込み、膜全体が硬くなってしまいます。
酸化によって変形した脂質は、膜に「錆び」のようなダメージを与え、流動性を低下させます。
これらが多いと、細胞膜が「しなやかに動けない」状態になり、免疫のアンテナ性能が著しく落ちます。
機能の低下による不具合
私たちの身体では、すべての細胞が「自分(自己)」と「他人(非自己)」を見分ける力を持っています。この機能が正常に働くことで、免疫は外からの敵(ウイルスや細菌など)を正しく攻撃し、自分自身の細胞は傷つけずに守ることができます。
しかし、この「自他の区別」がうまくいかないと、免疫の働きが乱れてしまいます。具体的には:
- 外敵を見逃す
- 自分を攻撃する
ウイルスや細菌を十分に攻撃できず、感染症にかかりやすくなります。
自分の細胞を誤って攻撃してしまい、関節や内臓などに炎症が起きる「自己免疫疾患」のリスクが高まります。
さらに、免疫細胞はふだんから身体をパトロールしていますが、必要以上に戦闘モードが続くと、まるで戦いが終わったのに兵士が警備を続けて疲弊しているような状態になります。この「戦いが長引く炎症」は、身体の組織に負担をかけ、老化を早めたり、糖尿病や動脈硬化など生活習慣病のリスクを高める原因になります。
つまり、細胞が正しく「自分」と「他人」を見分ける力は、健康を守る最前線のセンサーです。日々の生活や食事、栄養が、この見分ける力を支えていることを覚えておくと、健康管理のヒントになります。
起こりやすい不調や目に見える変化
細胞膜の健康が乱れると、身体の中のバランスも崩れやすくなります。その結果、次のような症状や変化が現れることがあります。
| 疲れやすさや免疫の低下 | ちょっとした運動や仕事で疲れを感じやすくなったり、風邪をひきやすくなったり、傷や口内炎がなかなか治らないことがあります。これは、免疫細胞がスムーズに働きにくくなるためです。 |
|---|---|
| アレルギー症状の悪化 | 花粉症や食物アレルギーなど、もともとアレルギーを持っている方は、症状が強く出やすくなります。免疫のバランスが崩れ、身体が過敏に反応しやすくなることが関係しています。 |
| 肌のトラブル | 細胞膜の健康が損なわれると、肌も影響を受けます。赤みやかゆみ、乾燥、敏感肌などが現れやすくなり、いつものスキンケアの効果を実感しにくいこともあります。 |
| 腸内環境の乱れ | 腸は「第二の脳」とも呼ばれるほど、身体の健康に深く関わる重要な器官です。腸の働きは、腸の細胞の細胞膜の状態とも密接に結びついています。細胞膜が健康で柔軟な状態であると、栄養の吸収や老廃物の排出、腸内の免疫バランスがスムーズに保たれます。しかし、細胞膜の働きが乱れると、腸内の環境も乱れやすくなります。 |
その結果として、次のような変化が起こることがあります。
- 便秘や下痢など、便通のリズムが乱れる
- お腹の張りやゴロゴロ感、重さや不快感を感じる
- 腸内の善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れ、免疫や体調にも影響
つまり、腸内の「調子の良さ」は、細胞膜の健康と深くつながっており、腸の不調は身体全体の不調にもつながりやすいのです。
関連する疾患や症状、病態(病気につながる体内の状態)
自己免疫疾患(関節リウマチ、橋本病、1型糖尿病、潰瘍性大腸炎など)
| 説明 | 主な影響・特徴 | 日常との関連(注意喚起) |
|---|---|---|
| 本来攻撃すべきでない自分の細胞を免疫が攻撃する状態 | 関節・臓器の炎症、慢性的な痛み、機能低下 | 睡眠不足や慢性的なストレス、加工食品中心の食生活で症状が悪化しやすい可能性があります。 |
アレルギー疾患(花粉症、喘息、アトピー性皮膚炎)
| 説明 | 主な影響・特徴 | 日常との関連(注意喚起) |
|---|---|---|
| 無害な物質に対して免疫が過剰反応する状態 | くしゃみ、鼻水、咳、皮膚のかゆみ・炎症 | 添加物や超加工食品で腸内環境が乱れると、症状が強く出ることもあります。 |
慢性炎症関連(動脈硬化、メタボリックシンドローム、アルツハイマー病リスク上昇)
| 説明 | 主な影響・特徴 | 日常との関連(注意喚起) |
|---|---|---|
| 体内で慢性的に炎症が続き、臓器や血管に負担がかかる状態 | 動脈硬化、血流悪化、内臓脂肪蓄積、認知機能低下リスク | 高脂肪・高糖質の食事、運動不足、睡眠不足が炎症を助長する可能性があります。 |
がん
| 説明 | 主な影響・特徴 | 日常との関連(注意喚起) |
|---|---|---|
| 免疫の「異物検知能力」が低下し、異常細胞を見逃す状態 | がん細胞の増殖・転移リスク上昇、免疫監視機能低下 | 加工食品や酸化した油の多い食生活、慢性的ストレスや睡眠不足でリスクが高まる可能性があります。 |
美容・アンチエイジング面での影響
免疫の誤作動や慢性炎症は「老化を早める隠れた要因」です。
- 炎症と肌の老化
- バリア機能低下と敏感肌
- 活性酸素と肌トラブル
- 健康な免疫調整が守るもの
- 若々しくハリのある肌
- 抜けにくくツヤのある髪
免疫の誤作動や慢性炎症が続くと、肌のコラーゲンやエラスチンが分解されやすくなります。その結果、シワやたるみが進行し、見た目の老化を加速させます。
細胞膜や皮膚のバリア機能が弱まると、外部刺激に対して敏感になり、赤みや乾燥、かゆみが目立つようになります。肌の潤いや守る力が低下するため、日常のダメージを受けやすくなります。
慢性的な炎症は活性酸素の増加を招きます。これにより、シミやくすみ、透明感の低下などが起こり、肌の美しさが損なわれます。
免疫が適切に働き、炎症が必要以上に起きない状態を保つことで、
を支える基盤となります。
今回のまとめ
細胞にとって「自他の区別」とは、自分自身の細胞と、外から侵入してくる異物(ウイルスや細菌など)を正しく見分けるための仕組みです。
この仕組みが正確に働くことで、免疫は必要なときにだけ適切に反応し、過剰な攻撃や誤作動(自己免疫反応)を防ぐことができます。
そして、私たちの生活習慣や食事内容は、細胞膜の健康状態に大きく影響します。細胞膜は、まさに「免疫の目印」を掲げる場所であり、この膜の柔軟性や構造が損なわれると、免疫が正しく自他を識別する力が弱まります。
結果として、免疫の働きが乱れ、慢性的な炎症や不調、病気のリスクが高まるだけでなく、肌や髪、身体全体の老化といった美容面にも影響が現れます。つまり、身体や美容の不調は、まず細胞膜レベルでの「識別精度の低下」から始まっている、と考えられます。
日々の生活で細胞膜を守り、柔軟で安定した状態を保つことが、免疫を正しく調整し、健康と若々しさを維持するための重要なポイントです。
クリルオイルに多く含まれる「リン脂質型オメガ3(EPA・DHA)」は、身体の細胞膜にそのまま取り込まれやすい特徴があります。
細胞膜がしなやかで安定していると、免疫細胞は自分と異物をきちんと見分けやすくなり、必要なときにだけ正しく反応できるようになります(※参考:21,22,23)。
さらに、オメガ3は炎症をおだやかにする働きがあり、免疫が過剰に反応しすぎるのを和らげながら、普段の健康な免疫の働きをサポートすることが期待されます(※参考:24,25,26,27)。
つまり、クリルオイルは「正しく働く免疫」と「炎症に振り回されない若々しさ」を支える「南極海からの恵み」といえます。
~ お知らせ ~
「細胞膜の9つの役割」をご説明した後、弊社団の最高科学顧問・矢澤一良博士に皆様のご質問をお訊きする新企画『矢澤博士に聞いてみた(仮題)』をスタートいたします。
そこで、読者の皆様から矢澤博士へのご質問を募集いたします。
食と健康について、またクリルオイルについてなど身近な疑問をお寄せください。
ご質問は、下記メールアドレスまでお送りください。
contents@krilloil.or.jp
-
- Niu SL, Mitchell DC, Litman BJ. Trans fatty acid derived phospholipids show increased membrane cholesterol and reduced receptor activation as compared to their cis analogs. Biochemistry. 2005 Mar 22;44(11):4458-65. doi: 10.1021/bi048319+. PMID: 15766276; PMCID: PMC1779501.
- Ali O, Szabó A. Review of Eukaryote Cellular Membrane Lipid Composition, with Special Attention to the Fatty Acids. Int J Mol Sci. 2023 Oct 28;24(21):15693. doi: 10.3390/ijms242115693. PMID: 37958678; PMCID: PMC10649022.
- Arnold M. Katz,
Should trans fatty acids be viewed as membrane-active drugs?,
Atherosclerosis Supplements,Volume 7, Issue 2,2006,Pages 41-42,ISSN 1567-5688,
https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosissup.2006.04.009.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567568806000353)
Abstract: Trans fatty acids (TFA) can modify cellular function by interacting with hydrophobic regions of membrane proteins. Because these interactions resemble those of pharmacological agents, it might be appropriate to view TFA as drugs.
Keywords: Arrhythmia; Diet; Heart disease; Lipids; Trans fatty acids - Naimi S, Viennois E, Gewirtz AT, Chassaing B. Direct impact of commonly used dietary emulsifiers on human gut microbiota. Microbiome. 2021 Mar 22;9(1):66. doi: 10.1186/s40168-020-00996-6. PMID: 33752754; PMCID: PMC7986288.
- Chassaing B, Compher C, Bonhomme B, Liu Q, Tian Y, Walters W, Nessel L, Delaroque C, Hao F, Gershuni V, Chau L, Ni J, Bewtra M, Albenberg L, Bretin A, McKeever L, Ley RE, Patterson AD, Wu GD, Gewirtz AT, Lewis JD. Randomized Controlled-Feeding Study of Dietary Emulsifier Carboxymethylcellulose Reveals Detrimental Impacts on the Gut Microbiota and Metabolome. Gastroenterology. 2022 Mar;162(3):743-756. doi: 10.1053/j.gastro.2021.11.006. Epub 2021 Nov 11. PMID: 34774538; PMCID: PMC9639366.
- Singh RK, Wheildon N, Ishikawa S. Food Additive P-80 Impacts Mouse Gut Microbiota Promoting Intestinal Inflammation, Obesity and Liver Dysfunction. SOJ Microbiol Infect Dis. 2016;4(1):10.15226/sojmid/4/1/00148. doi: 10.15226/sojmid/4/1/00148. Epub 2016 Jun 1. PMID: 27430014; PMCID: PMC4944853.
- リン脂質非対称性により制御される細胞膜ステロールの保持機構
Journal of Japanese Biochemical Society 94(1): 82-86 (2022)
doi:10.14952/SEIKAGAKU.2022.940082 - Monteiro KKAC, Shiroma ME, Damous LL, Simões MJ, Simões RDS, Cipolla-Neto J, Baracat EC, Soares-Jr JM. Antioxidant Actions of Melatonin: A Systematic Review of Animal Studies. Antioxidants (Basel). 2024 Apr 7;13(4):439. doi: 10.3390/antiox13040439. PMID: 38671887; PMCID: PMC11047453.
- Kopustinskiene DM, Bernatoniene J. Molecular Mechanisms of Melatonin-Mediated Cell Protection and Signaling in Health and Disease. Pharmaceutics. 2021 Jan 20;13(2):129. doi: 10.3390/pharmaceutics13020129. PMID: 33498316; PMCID: PMC7909293.
- Davinelli S, Medoro A, Savino R, Scapagnini G. Sleep and Oxidative Stress: Current Perspectives on the Role of NRF2. Cell Mol Neurobiol. 2024 Jun 25;44(1):52. doi: 10.1007/s10571-024-01487-0. PMID: 38916679; PMCID: PMC11199221.
- Besedovsky L, Lange T, Born J. Sleep and immune function. Pflugers Arch. 2012 Jan;463(1):121-37. doi: 10.1007/s00424-011-1044-0. Epub 2011 Nov 10. PMID: 22071480; PMCID: PMC3256323.
- Garbarino S, Lanteri P, Bragazzi NL, Magnavita N, Scoditti E. Role of sleep deprivation in immune-related disease risk and outcomes. Commun Biol. 2021 Nov 18;4(1):1304. doi: 10.1038/s42003-021-02825-4. PMID: 34795404; PMCID: PMC8602722.
- Zhai X, Wang J, Sun J, Xin L. PM2.5 induces inflammatory responses via oxidative stress-mediated mitophagy in human bronchial epithelial cells. Toxicol Res (Camb). 2022 Jan 19;11(1):195-205. doi: 10.1093/toxres/tfac001. PMID: 35237424; PMCID: PMC8882786.
- Ulintz, Lea1; Sun, Qinghua1,2,3,. Ambient particulate matter pollution on lipid peroxidation in cardiovascular diseases. Environmental Disease 1(4):p 109-117, Oct–Dec 2016. | DOI: 10.4103/2468-5690.198616
- Zhang, M., Wang, Y., Hu, S. et al. Causal relationships between air pollution and common autoimmune diseases: a two-sample Mendelian randomization study. Sci Rep 15, 135 (2025).
https://doi.org/10.1038/s41598-024-83880-9 - Adami G, Pontalti M, Cattani G, Rossini M, Viapiana O, Orsolini G, Benini C, Bertoldo E, Fracassi E, Gatti D, Fassio A. Association between long-term exposure to air pollution and immune-mediated diseases: a population-based cohort study. RMD Open. 2022 Feb;8(1):e002055. doi: 10.1136/rmdopen-2021-002055. PMID: 35292563; PMCID: PMC8969049.
- Haidar Z, Fatema K, Shoily SS, Sajib AA. Disease-associated metabolic pathways affected by heavy metals and metalloid. Toxicol Rep. 2023 Apr 24;10:554-570. doi: 10.1016/j.toxrep.2023.04.010. PMID: 37396849; PMCID: PMC10313886.
- Rio P, Gasbarrini A, Gambassi G, Cianci R. Pollutants, microbiota and immune system: frenemies within the gut. Front Public Health. 2024 May 10;12:1285186. doi: 10.3389/fpubh.2024.1285186. PMID: 38799688; PMCID: PMC11116734.
- Devi, A.; De Silva, Y.S.K.; Tyagi, L.; Aaryashree. The Individual and Combined Effects of Microplastics and Heavy Metals on Marine Organisms. Microplastics 2025, 4, 38.
https://doi.org/10.3390/microplastics4030038 - Dan KB, Yoo JY, Min H. The Emerging Threat of Micro- and Nanoplastics on the Maturation and Activity of Immune Cells. Biomol Ther (Seoul). 2025 Jan 1;33(1):95-105. doi: 10.4062/biomolther.2024.195. Epub 2024 Dec 12. PMID: 39663987; PMCID: PMC11704408.
- Garcia C, Andersen CJ, Blesso CN. The Role of Lipids in the Regulation of Immune Responses. Nutrients. 2023 Sep 7;15(18):3899. doi: 10.3390/nu15183899. PMID: 37764683; PMCID: PMC10535783.
- Zhang T, Hu W, Chen W. Plasma Membrane Integrates Biophysical and Biochemical Regulation to Trigger Immune Receptor Functions. Front Immunol. 2021 Feb 19;12:613185. doi: 10.3389/fimmu.2021.613185. PMID: 33679752; PMCID: PMC7933204.
- Calder PC. The relationship between the fatty acid composition of immune cells and their function. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2008 Sep-Nov;79(3-5):101-8. doi: 10.1016/j.plefa.2008.09.016. Epub 2008 Oct 23. PMID: 18951005.
- Poggioli R, Hirani K, Jogani VG, Ricordi C. Modulation of inflammation and immunity by omega-3 fatty acids: a possible role for prevention and to halt disease progression in autoimmune, viral, and age-related disorders. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2023 Aug;27(15):7380-7400. doi: 10.26355/eurrev_202308_33310. PMID: 37606147.
- Bodur M, Yilmaz B, Ağagündüz D, Ozogul Y. Immunomodulatory Effects of Omega-3 Fatty Acids: Mechanistic Insights and Health Implications. Mol Nutr Food Res. 2025 May;69(10):e202400752. doi: 10.1002/mnfr.202400752. Epub 2025 Mar 30. PMID: 40159804; PMCID: PMC12087734.
- Hong K, Hun M, Wu F, Mao J, Wang Y, Zhu J, Zhou X, Xie H, Tian J, Wen C. Association between Omega-3 fatty acids and autoimmune disease: Evidence from the umbrella review and Mendelian randomization analysis. Autoimmun Rev. 2024 Nov;23(11):103651. doi: 10.1016/j.autrev.2024.103651. Epub 2024 Sep 30. PMID: 39357585.
- Calder PC. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: from molecules to man. Biochem Soc Trans. 2017 Oct 15;45(5):1105-1115. doi: 10.1042/BST20160474. Epub 2017 Sep 12. PMID: 28900017.
過去の記事を読む
- [Vol.18]
健康を基本から見直す“脂質ケア”という新習慣 - [Vol.17]
冬に知っておきたい脂肪の新常識!減らすより整える。身体が自然に選ぶ脂肪の正しい活用法 - [Vol.16]
身体の“だるさ”の季節リレーを止める!身体のスイッチを入れて、季節を超えて元気になる - [Vol.15]
季節を超えて続く“夏疲れ”。秋冬の不調、その正体は? - [Vol.14]
胃もたれとあぶら(脂質)の関係 -オメガ3脂肪酸の形(構造)は1種類ではない - [Vol.13]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part11 - [Vol.11]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part9 - [Vol.10]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part8 - [Vol.9]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part7 - [Vol.8]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part6 - [Vol.7]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part5 - [Vol.6]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part4 - [Vol.5]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part3 - [Vol.4]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part2 - [Vol.3]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part1 - [Vol.2]
細胞レベルで健康をサポートするクリルオイル - [Vol.1]
クリルの生態とクリルオイルの魅力について