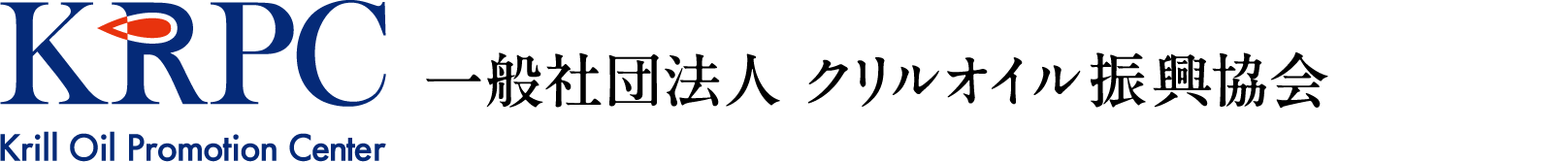KRPC Ambassador Letter クリルオイルの健康促進と疾病予防の最新情報
[Vol.13] 健康な細胞が、健康な身体をつくる Part11 - 最終回 -生命を支える“静かな管理人”ー細胞膜がつくる体内の調和
前回(Vol.12)までは、細胞膜の9つの役割のうち
「1.物質の選択的透過性」
「2.情報伝達(シグナル伝達)」
「3.細胞の保護・防御機能:守りの壁」
「4.細胞の形状保持と構造の保持:袋と骨組み」
「5.細胞間のコミュニケーション:他の細胞との「チームプレー」」
「6.エネルギー代謝・物質輸送:栄養やエネルギーの“通路”」
「7.細胞の増殖や分化の調節:成長や分裂をコントロール」
「8.細胞の識別と免疫の調整:自他の区別」
について取り上げ、それらの特徴が損なわれた場合に身体にどのような不調や影響が出るのかをお伝えしました。
今回は、細胞膜の役割の最終回「9.細胞内外の環境のバランス維持:恒常性の維持」についてご説明していきます。
生命を支える“静かな管理人”ー細胞膜がつくる体内の調和
私たちの身体は、外部環境や生活習慣の影響を常に受けながらも、体内の状態を安定して保つ仕組みがあります。これを「恒常性(ホメオスタシス)」と呼びます。体温や血糖、血液の水分量、pH、栄養の濃度などがある程度一定に保たれるのは、この恒常性のおかげです。
ここでいう「外部環境や生活習慣」とは、例えば次のようなものです。
| 食事内容 | 栄養バランスや糖質・脂質の過不足 |
|---|---|
| 睡眠の質や時間 | 慢性的な睡眠不足や不規則な生活 |
| 運動量 | 過度の運動や運動不足 |
| ストレス | 仕事や人間関係、精神的な緊張 |
| 気温・湿度の変化 | 暑さ・寒さや湿度の極端な変化 |
| 紫外線や大気汚染 | 肌や体内の酸化ストレスを増やす外部要因 |
これらの影響を受けても、身体は恒常性を維持し、血糖値や体温、体液の濃度などを適切にコントロールしています。
細胞膜は、この恒常性を支える重要な存在です。これまでご紹介した1~8の細胞膜の役割は、それぞれが個別に働く「各部署のスタッフ」のようなものです。具体的には、次の通りです。
- 物質の選択的透過
- 情報伝達
- 細胞の保護・防御
- 細胞の形状保持・構造維持
- 細胞間のコミュニケーション
- エネルギー代謝・物質輸送
- 細胞の増殖や分化の調整
- 細胞の識別と免疫の調整
必要な栄養や水分を取り入れ、不要な物質や老廃物を排出する
外部からの刺激や信号を受け取り、その情報を細胞内に伝えて、適切な反応を起こす
外部からの攻撃や有害物質から細胞を守る
細胞の形や安定性を保つ
他の細胞との連携や情報交換を可能にする
生命活動に必要なエネルギーや物質を運ぶ
細胞の成長や機能分化をコントロールする
自己と非自己を区別し、免疫反応を適切に管理する
これら1~8の個別の働きが適切に機能することで、細胞は健康に働き、身体全体の調和に寄与します。
そして今回9番目の役割「細胞内外の環境のバランスを整える力(恒常性の維持)」は、これまでの1~8の役割をまとめる「マネージャー」のような存在です。
各個別機能がスムーズに働くよう調整し、細胞の中と外の環境(栄養や水分、イオン、老廃物、化学バランス)を最適に保つことで、身体全体の“チームワーク”を円滑にし、日々の活動がスムーズに行える状態に保ちます。言い換えれば、各部署がバラバラに動くのではなく、全体が協力して効率よく働くように管理しているのが、この9番目の役割です。
今回は、細胞膜が担っている9つの役割のうち、「細胞内外の環境のバランス維持:恒常性の維持」についての機能が損なわれたときに、私たちの身体にはどのような不調や変化が現れるのかをご説明していきます。
【細胞膜の9つの役割】
恒常性のいろは。
- 一言でいうと
- 恒常性の基本的な役割とは
- 恒常性の仕組みとは
- センサー(感知)
- 調整機構(フィードバック)
- 効果器
* (実行部隊) - 対象の範囲は?
「身体の安定維持力」、「身体を元に戻す力」 のことです。
身体の内部環境(体温、血糖値、pHなど)を安定させ、身体や細胞が正常に働くための基盤を作ることです。これを維持することによって、環境の変化やストレスに応じて身体の状態を調整し、健康を守り、生命活動を安定させることになります。
外部の影響にただ反応するのではなく、身体や細胞の状態を適正に保つことを優先します。
恒常性は「センサー(感知)」と「調整機構」の働きで成立します。
身体の状態を常にモニター(監視)します。
例:体温を測る視床下部のセンサー、血糖値を測る膵臓のセンサー。
状態が変わったら、元に戻すよう指令を出します。
例1:血糖の調整
血糖値が高い → インスリン分泌 → 血糖値を下げる
例2:炎症の調整(オメガ3が関わるフィードバック)
炎症が起こる → 免疫細胞が活性化し、炎症反応を促す物質(サイトカインなど)を放出 →回復段階になると、オメガ3脂肪酸から作られる「抗炎症性のメディエーター(レゾルビン、プロテクチンなど)」が働き、炎症を鎮めて元の状態に戻すよう指令を出します。
オメガ3は「炎症を起こす側」ではなく、「炎症が長引かないように終息させる」ための調整役として働いています。
指令に従い、器官や細胞が変化を起こします。
例:汗をかく、心拍数を上げる、糖を筋肉や肝臓に取り込みます。
*効果器(こうかき)=指令を受けて、体の働きを変える器官や細胞のこと。
恒常性は全身レベルと細胞レベルで働きます。
下記の表の左側の身体レベルは全身の大きな調整、右側の細胞レベルは細胞個々の局所調整です。
- 身体の恒常性は全体のバランスを保つ大枠
- 細胞の恒常性は各細胞が自律的に調整
- 相互依存
→ 体温、血糖、血圧など、複数の臓器やシステムが連携して制御します。
→ 細胞膜や代謝系(エネルギーをつくり、不要な物質を分解・処理する仕組み)などが、細胞の内部やまわりの状態(栄養や酸素、老廃物など)を安定させます。
→ 身体レベルの恒常性が保たれることで、細胞は安定した環境で機能できます。
また、細胞が正常に働くことで、臓器や全身の恒常性が維持されるという相互依存の関係にあります。

《身体レベルと細胞レベルの恒常性の対比》
| 身体レベルの恒常性 | 細胞レベルの恒常性 | |
|---|---|---|
| 体温の維持 | 体温を36.5〜37℃前後に保つ。暑いと汗をかき、寒いと震えます。 | 細胞内の温度を安定させ、酵素(身体の中でさまざまな反応を助けるタンパク質)や代謝反応(エネルギーをつくったり、不要な物質を分解したりする働き)が最適に働く温度を維持。細胞膜の流動性やタンパク質構造を保ちます。 |
| 血糖値の維持 | 食後はインスリンで血糖を貯蔵、空腹時はグルカゴン*で血糖を補充します。 | 細胞内エネルギー管理、グルコース取り込みとATP*産生を調整します。過不足を避け、エネルギー供給を安定させます。
*ATP(アデノシン三リン酸):細胞内でエネルギーを運ぶ“エネルギー通貨”のような物質です。食べ物から得たエネルギーを一時的に蓄え、筋肉の動きや代謝、細胞内のさまざまな反応に使われます。 |
| 血圧の維持 | 血管の収縮・拡張や心拍数で血流を安定化。 | 細胞内圧の維持(浸透圧の調整)ナトリウム・カリウムポンプで細胞内外の水分バランスを調整します。 |
| 呼吸の調整 | 酸素不足や二酸化炭素過多に応じて呼吸を調整。 | ミトコンドリアで酸素を効率よく使い、体内のエネルギーの働きを安定させながら、酸化ストレスを抑えます。 |
| 水分・塩分の調整 | 腎臓で水分・塩分を排出・保持。 | 細胞内液の恒常性イオン濃度やpHを調整して代謝や細胞膜機能を安定化させます。 |
| 免疫の調整 | 感染や炎症に応じて全身の免疫活動を適切に調整。 | 細胞の防御・自己認識異物やウイルス侵入時に防御応答を起こし、自己成分は攻撃しないように制御します。 |
| ホルモン調整 | 必要に応じてホルモン量を増減。 | 受容体・情報伝達制御ホルモンやシグナル分子(身体の中でメッセージを運ぶ物質)に応答し、細胞活動を適切に変化させる。 |
*グルカゴン:膵臓から出るホルモンで、血糖値を上げる働きがあります。身体がエネルギー不足のときに、肝臓からブドウ糖を出すサポートをします。
身体の恒常性は、細胞の恒常性が積み重なった結果でもあります。
- 仕組みの特徴
- 食後に血糖値が上がると → インスリンが分泌され → 血糖値を下げる方向に働きます。
- 血糖値が下がりすぎると → グルカゴンが分泌され → 血糖値を上げる方向に働きます。
- まとめ
- 感知 → 調整 → 実行のサイクルで成り立ちます。
- 細胞と全身の両方で働きます。
- 健康維持の「基本」であり、生命活動の「基盤」です。
「負のフィードバック」が基本
「変化した状態を元に戻す」ように身体が自動で働くことです。
例:血糖値の調整
適応能力がある
環境が変わっても、身体は少しずつ調整して安定を保ちます。
恒常性は「生命の安定を守る力」。
9.細胞内外の環境のバランス維持:恒常性の維持
生活習慣や生活環境による影響の可能性
日常生活や周囲の環境が細胞のバランスに影響します。
- 睡眠不足の影響
- 成長ホルモンの分泌が低下
- 睡眠中、とくに深い眠り(ノンレム睡眠)の間に成長ホルモンが分泌されます。
- 成長ホルモンは、細胞の修復や新しい細胞の生成、筋肉や皮膚の再生などをサポートします。
- 睡眠不足だと、この分泌が十分に行われず、細胞の修復や再生が遅くなります。
- 細胞の修復機能が弱まる
- 細胞は日中にダメージを受けます(紫外線や酸化ストレス、代謝による影響など)。
- 睡眠中に、これらのダメージを修復するプロセスが活発に行われます。
- 睡眠不足では修復時間が足りず、細胞の疲労や不調が蓄積されます。
- 細胞の調整力(恒常性の維持力)が低下
- 細胞膜や細胞内のシステムは、栄養や酸素、老廃物のバランスを整える役割を持っています。
- 十分な睡眠がとれないと、この調整機能が弱まり、細胞が最適な状態を保てなくなります。
- 結果として、免疫力低下や代謝異常、肌荒れ、疲労感などにつながります。
- 偏った食事の影響
- 糖質を摂りすぎると
- 血糖値が急上昇し、細胞は余分な糖を処理しようとします。余った糖は脂肪として蓄えられ、エネルギー代謝のバランスが乱れます。また、過剰な糖はたんぱく質と結びつき、細胞を老化させる「糖化反応」も起こります。
→ 結果として「疲れやすい」「肌がくすむ」「集中力が落ちる」といった不調が出やすくなります。 - 脂質の種類や摂り方が偏ると
- 脂質は本来、エネルギー源、細胞膜やホルモンの材料となる大切な栄養素です。しかし、揚げ物や加工食品などに含まれていることがあるといわれている「トランス脂肪酸」や「酸化した油」を多く摂ると、細胞膜の質が変化して硬くなり、しなやかさを失うことがあります。
- 細胞膜が硬くなると、栄養や情報のやりとりがスムーズに行えず、細胞の働き全体が鈍くなり、体の調整力や防御力にも影響が及びます。
- 一方で、青魚やクリルオイルなどに含まれる良質な脂質(オメガ3系脂肪酸)は、細胞膜をやわらかく保ち、情報伝達や炎症の抑制を助けます。
→ つまり、脂質は「量」だけではなく「種類」と「摂り方のバランス」が大切です。
良質な脂を適度に摂ることで、細胞はむしろ健康でしなやかになります。 - 野菜・ミネラルが不足すると
- 野菜には、細胞の代謝や修復を助けるビタミン・抗酸化成分が豊富に含まれています。これが不足すると、細胞内で発生する活性酸素を処理できず、細胞が酸化しやすくなります。
- さらに、ミネラル(亜鉛・マグネシウム・鉄・カルシウムなど)は、細胞内の酵素反応やエネルギー産生、神経伝達を支える重要な栄養素です。
不足すると、細胞が正常に機能できなくなり、
→ 「代謝の低下」「ホルモンバランスの乱れ」「免疫の低下」などを招きます。 - 運動不足の影響
- ストレスの影響
- ストレスの発生
- 精神的・身体的な負荷(仕事、睡眠不足、過労など)がかかります。
- 脳が「危険信号」と認識し、ホルモン分泌を指示します。
- ストレスホルモンの増加
- 主に コルチゾール や アドレナリン が分泌されます。
- これらは短期的には身体を守る役割があります(戦う、あるいは逃げる反応)。
- 細胞内の化学環境への影響
- ストレスホルモンは 細胞内のカルシウムやイオンバランスを変化させます。
- 酸化ストレスが増え、細胞膜やタンパク質がダメージを受けやすくなります。
- エネルギー管理への影響
- ミトコンドリアの働きが低下し、身体へのエネルギー供給が不安定になります。
- 栄養や酸素の利用効率が下がるため、疲労感や回復力低下につながります。
- エ細胞内情報伝達の乱れ
- ホルモンや神経伝達物質のシグナルが正確に伝わりにくくなります。
- 結果として免疫反応や代謝、修復機能がスムーズに行われなくなります。
- 恒常性(バランス維持機能)の低下
- 細胞内外の状態を安定化させる力が弱まると、細胞や身体の働きが不安定になります。
- 長期的には炎症や老化、免疫力低下などのリスクが高まります。
- 外的環境の影響
- 高温
- 影響:体温が上がることで、細胞のタンパク質構造や酵素の働きが乱れやすくなります。
- 具体例:熱中症、疲労感、皮膚の乾燥や赤み。
- 低温
- 影響:細胞の活動が鈍くなり、血流が悪化しやすいです。
- 具体例:手足の冷え、代謝の低下、肌のかさつき。
- 紫外線
- 影響:DNAや細胞膜を傷つけ、活性酸素を増やします。
- 具体例:日焼け、しみ・しわの原因、肌の老化。
- 化学物質
- 影響:有害物質が細胞に入り込み、炎症や酸化ストレスを引き起こします。
- 具体例:農薬、洗剤、排気ガス、食品に含まれる人工的な成分などによるアレルギー反応や肌トラブル。
- 空気汚染
- 影響:微粒子や有害ガスが呼吸を通して体内に入り、細胞や免疫に負担をかけます。
- 具体例:呼吸器の不調、慢性的な疲れ、肌のくすみ。
睡眠は「細胞の夜のメンテナンス時間」です。夜間に成長ホルモンが“修理スタッフ”として働き、細胞の破損を直します。しかし、睡眠不足となると修理スタッフ不足のような状態となり、細胞の調整力が弱まるため、身体全体が疲れやすくなります。
私たちの身体は、数十兆個の細胞からできています。
その一つひとつの細胞が正常に働くためには、糖質・脂質・たんぱく質に加え、ビタミンやミネラルといった補助的な栄養素が欠かせません。
ところが、糖質や脂質の摂りすぎ、野菜やミネラルの不足が続くと、細胞内の栄養バランスが崩れ、エネルギー生産や老廃物の排出、情報伝達、修復・増殖など、細胞の基本的な働きが乱れてしまいます。
運動不足になると、筋肉の動きが少なくなり、血液を全身に送り出す力が弱まります。その結果、身体の血液の流れ(血流)がゆっくりになったり滞ったりします。
血液は体中の細胞に酸素や栄養を届ける役割があるので、血液の流れが悪いと、必要な酸素や栄養が細胞まで届きにくくなります。その結果、細胞は元気に働きにくくなり、疲れやすくなったり、体の調子が整いにくくなったりします。
細胞膜への影響
細胞膜は、細胞の内外の環境を調整する重要な役割を持っています。柔軟で健康な状態であれば、必要な栄養や酸素を効率よく取り込み、老廃物や余分な水分を排出することができます。しかし、次のような影響で細胞膜の働きは低下します。
| 酸化ストレス | 活性酸素が細胞膜の脂質を攻撃すると、細胞膜の構造が傷つき柔軟性が失われます。細胞膜が硬くなると、栄養や酸素の取り込みがスムーズに行えず、老廃物の排出も滞ります。その結果、細胞の働き全体が弱まり、疲労や炎症が起こりやすくなります。 |
|---|---|
| 炎症 | 長期間の炎症は、細胞膜のタンパク質や脂質の構造を乱し、物質の出入りの通路がうまく働かなくなります。栄養や酸素の供給が滞り、不要な物質が蓄積されることで、細胞の働きが低下します。 |
| 脂質の種類や バランスの乱れ |
細胞膜はリン脂質を中心に構成されており、特に不飽和脂肪酸(オメガ3など)は細胞膜を柔軟に保つために重要です。しかし、食事の偏りや加齢により、細胞膜に必要な脂肪酸のバランスが崩れることがあります。
|
酸化ストレスや炎症、脂肪酸バランスの乱れにより、細胞は十分に栄養や酸素を受け取れず、老廃物がたまりやすくなります。その結果、細胞内の環境が安定しにくくなり、免疫や修復機能だけでなく、全身の健康状態にも影響が及びます。
機能の低下による不具合
細胞のバランス調整力が弱まると、体内で以下のような不具合が生じます。
- 細胞ストレス(細胞にかかる負担やダメージ)耐性の低下
- 酸化ストレスや外的刺激への適応力が弱まり、細胞の損傷回復が遅れます。
- 活性酸素や有害物質による慢性的なダメージが蓄積しやすくなります。
- 栄養素や酸素の供給効率の低下
- 必要な物質の取り込みが滞ることで、細胞のエネルギー産生が効率的に行えなくなります。
- 酸化ストレスが増えやすく、細胞内の損傷修復機能が弱まります。
- 老廃物や余分な水分の排出不全
- 細胞内外の浸透圧バランスが乱れ、細胞がむくみやすい状態になります。
- 細胞内の代謝副産物の蓄積が増え、ミトコンドリアや酵素の働きが鈍化します。
- 代謝関連反応の低下(エネルギーや物質のやり取りの効率低下)
- 栄養の分解・吸収・合成に関わる酵素の活性が低下し、細胞レベルでの物質循環が滞ります。
- エネルギー産生の効率が下がることで、細胞の修復や成長が遅くなります。
- 免疫機能の局所的低下
- 細胞膜上の受容体や情報伝達機構の働きが弱まると、異物や病原体への初期対応が遅れます。
- 結果として、炎症反応が過剰または不十分になるリスクが高まります。
- 細胞内情報伝達の不調
- ホルモンや神経伝達物質の受容やシグナル伝達が滞り、細胞間の連携が乱れます。
- 長期的には、組織や臓器レベルでの調整力にも影響を及ぼします。
- 細胞ストレス耐性の低下
- 酸化ストレスや外的刺激への適応力が弱まり、細胞の損傷回復が遅れます。
- 活性酸素や有害物質による慢性的なダメージが蓄積しやすくなります。
起こりやすい不調や目に見える変化
細胞レベルのバランスの乱れは、日常で次のように感じられます。
| 体調面 | 疲れやすい、だるさの増加 肩こり、頭痛、むくみ、便秘などの症状の増加 |
|---|---|
| 脳・神経面 | 集中力の低下 眠りの質の低下 イライラや気分の変動の増加 |
| 肌 | 水分保持力の低下 弾力の低下によるシワやたるみ くすみや乾燥感の増加 |
| 髪・爪 | 髪のパサつき切れやすさの増加 爪の割れやすさ、もろさの増加 |
関連する疾患や症状、病態(病気につながる体内の状態)
| 分類 | 具体例 | 説明・補足 |
|---|---|---|
| 生活習慣病 | 高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満 | 細胞の栄養や代謝のバランスが乱れることで発症リスクが高まります。 |
| 免疫・炎症 関連 |
慢性炎症、感染症リスクの増加、自己免疫疾患(例:関節リウマチ) | 細胞間のコミュニケーションや免疫調整機能が低下すると、炎症や免疫異常が起こりやすくなります。 |
| 循環器・神経系 | 動脈硬化、心血管疾患、認知機能低下、脳血管障害 | 細胞レベルの酸素や栄養の供給不足、老廃物の蓄積が血管や神経に影響します。 |
| 代謝・内分泌 | 脂肪肝、甲状腺機能異常 | 細胞のエネルギーやホルモン調整が乱れることで代謝異常が起こります。 |
| その他 全身影響 |
肌の老化、疲労感、むくみ | 細胞のバランスが崩れると、外見や日常の体調にも影響します。 |
美容・アンチエイジング面での影響
細胞が健康な環境を維持できないと、肌や髪、爪だけでなく、全身の老化スピードにも影響が現れます。
| 肌 | 水分保持力や弾力の低下、シワやたるみの増加、くすみや透明感の低下。肌のバリア機能も弱まり、外的刺激に敏感になることがあります。 |
|---|---|
| 髪 | コシやツヤの低下、抜け毛や細毛の増加、乾燥や枝毛が起こりやすくなる。 |
| 爪 | もろくなったり、割れやすくなる。 |
| 身体全体 | 細胞の修復力や代謝力が低下することで、疲れやすくなり、老化のスピードが速まる。免疫力の低下も起こりやすく、健康的な若々しさが保ちにくくなります。 |
今回のまとめ
細胞膜は、私たちの身体の中で環境を最適に保つ“調整役”として働きます。
その「9つの役割」について今回までお伝えしてきました。
健康的な生活習慣や適切な栄養で細胞膜の柔軟性と機能を維持することは、これら9つの働きを支えることにつながります。
結果として・・・
- 栄養や酸素、老廃物のやり取りがスムーズになります。
- 疲れにくい身体や健康的な肌を維持しやすくなります。
- 生活習慣病のリスクを抑える助けになります。
といった身体全体の健康効果につながります。
つまり、日々の生活で細胞膜のバランスを守ることは、目に見えない身体の調整力を支える助けとなり、毎日の健康や美しさの土台を整えることにもつながります。
クリルオイルは、リン脂質型オメガ3脂肪酸を含み、細胞膜の柔軟性を保つことで、細胞が本来の働きを発揮しやすい環境づくりを支えます。
- 柔軟性の維持
- 抗炎症・抗酸化サポート
- 美容面でのサポート
栄養や酸素の取り込み、老廃物の排出をスムーズに保つように働きます。
EPA、DHA、アスタキサンチンが、炎症や酸化による細胞への負担をやわらげる働きを支えます。
肌や髪、爪の健やかさを保ち、年齢サインの目立ちにくい状態へ導きます。
クリルオイルを取り入れることで、細胞本来の働きを支え、健康維持と美容サポートの両面に役立ちます。
~ お知らせ ~
次回から弊社団の最高科学顧問・矢澤一良博士に皆様のご質問をお訊きする新企画『矢澤博士に聞いてみた(仮題)』をスタートいたします。
そこで、読者の皆様から矢澤博士へのご質問を募集いたします。
食と健康について、またクリルオイルについてなど身近な疑問をお寄せください。
ご質問は、contents@krilloil.or.jpまでお送りください。
過去の記事を読む
- [Vol.18]
健康を基本から見直す“脂質ケア”という新習慣 - [Vol.17]
冬に知っておきたい脂肪の新常識!減らすより整える。身体が自然に選ぶ脂肪の正しい活用法 - [Vol.16]
身体の“だるさ”の季節リレーを止める!身体のスイッチを入れて、季節を超えて元気になる - [Vol.15]
季節を超えて続く“夏疲れ”。秋冬の不調、その正体は? - [Vol.14]
胃もたれとあぶら(脂質)の関係 -オメガ3脂肪酸の形(構造)は1種類ではない - [Vol.12]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part10 - [Vol.11]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part9 - [Vol.10]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part8 - [Vol.9]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part7 - [Vol.8]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part6 - [Vol.7]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part5 - [Vol.6]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part4 - [Vol.5]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part3 - [Vol.4]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part2 - [Vol.3]
健康な細胞が、健康な身体をつくる Part1 - [Vol.2]
細胞レベルで健康をサポートするクリルオイル - [Vol.1]
クリルの生態とクリルオイルの魅力について